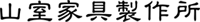| 素材のこと |
“about material”
わたしたちが主に使用している材料は世界でも優良材として認められている貴重な北海道産のミズナラ(どんぐりの木)です。
北海道産のミズナラ材の特長は冬期間雪に覆われることで風や寒さから保護され材が傷まなく、雪による保温効果によって適度な柔らかさを持つ材に成長します。
このような材が育成されるのは北海道の自然環境がもたらすことによるものです。
同じミズナラでも寒さが厳しい地方で育ったナラ材は成長も遅く、そのため木目が非常に詰まっており重たく硬い木となります。
北海道の森林面積は総面積の約7割といわれています。他県では類がないほど木に恵まれた暮らしをしています。
私たちは創業以来北海道で育ったミズナラを北海道民として森林を元気にしふるさとを元気にする「地材地消」を行っています。
| 乾 燥 |
「道産材の声を聞く。」
木材には多分に水分が含まれており、乾燥という行程は丈夫で歪みのない家具を製作するうえで重要なポイントとなっています。
まず初めに、木材の含水量(※1)が16~20%になるまで約1年天然乾燥させます。
次に、2~3週間の間、窯入れをし、さらに7~8%まで含水量を落とします。
その後一端、イコライジングとコンディショニングと呼ばれる作業を行い、含水量を8~9%に戻します。この工程は通称「戻し」と呼ばれるものです。
そうして最後に窯出しし、3日ほど冷やしてから家具材として使用します。
なぜ、含水量を戻す作業が必要なのかというと、材によって堅さや柔らかさに違いがあり、そのことによって水分量にも差があります。
また、この含水量は材の外側と中側でも変わってきます。
そこで、水分量を均一化するために、蒸気を加えるなどのイコライジング(※2)と、コンディショニング(※3)という温度・湿度を微調整する工程が必要となるのです。
実は乾燥という工程に置いて、この戻し作業が最も重要なものとなります。
この作業をしないと材料によって水分量にバラつきが生じ、狂いの起きやすい材料も混じってしまいます。
そのために窯入れ前に試験材として、堅い材や柔らかい材を選んで毎日重さを計り、その重量の差で水分量を割り出して調べています。
このとき、材料の中の水分量はオーブン計の中に試験材を入れ、一度すべての水分を抜き、抜く前と後との重量の差で計測しています。
正確な水分量を計ることが、乾燥という工程、ひいては狂いの少ない材料を作るために最も重要なポイントとなります。
※1 含水率 物質に含まれる水分の割合を示したもの
※2 イコライジング 材料の重さに対しての水分量の平均化する作業
※3 コンディショニング 材料の中・外の水分量の平均化をする作業
| 木取り |
「目利きと見立て。」
木取りとは、簡単にいうと材料の寸法を取る作業の事を指します。
しかし、寸法を取ると言っても、ただ寸法通りに切っていくのではなく、完成品をイメージしながら作業しなければいけません。
いかに木目が通るように作業するかで、製品の良し悪しが決まってしまうからです。
材料一枚一枚にも、人と同じように個性があり、色も違います。
「赤っぽい」「黒っぽい」「青っぽい」「白っぽい」などの微妙な色の違いがあったり「堅い」「柔らかい」などの硬度の違いがあったりと、材の個性は千差万別です。
それらを使って1つの完成品を作るには、材料の質や木目を見る長年の経験と勘が必要です。
私たちの家具作りでは一部を除いて大部分で無垢材を使用しますので、外から見える部材はもちろんですが、見えにくい部材にも気を遣って木取り作業を行っています。
テーブルやデスクの天板部分を製作する際には、材料を「接ぐ(はぐ)」という一番重要な工程があります。
まずは「節(ふし)」や「白太(しらた)」(※1)という部分を削ぎとり、「木表」(※2)と「木裏」(※3)に注意しながら、余計な所を削ぎ落した材料を何枚か並べて、完成品が一枚の板に見えるよう木目を合わせ、最後に高周波という高圧電流によって特殊な糊を使用し瞬間接着させます。
こうした工程を経て、ようやく1枚の天板の素地が完成するのです。
※1 白太 丸太の外側の柔らかい部分の虫がいる可能性がある部分
※2 木表 丸太の外側の部分
※3 木裏 丸太の内側の部分