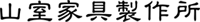| 仕上げのこと |
“about finish”
| 仕上げ |
「心地よさとは心配り。」
様々な粗さのサンドペーパーを何度も変えながら削ることで、その商品の良し悪しを左右する重要な作業です。
「部材」の段階である程度仕上げても「部品」の段階までいくと他の部材との段差ができていたり、細かなキズができてしまう可能性もあります。
それを徐々になくしていくのはもちろん、そこには使い手への想いがこめられているのです。
「心地よさとは心配り。」
これまで木取り、加工、組立てと説明してきましたが、実はこの作業の間には非常に重要で手間のかかる「仕上げ」という作業があります。
簡単にいうと仕上げとは、サンドペーパーによる研磨作業のことです。
部品の場所ごとにペーパーかけの回数や使用するペーパーの細かさがすべて異なりますが、代表的な扉の仕上げだと6回もの研磨作業が必要になります。
まず1回目は木取り後の部材を粗めのペーパーで荒削りします。もちろんどんなに部材が多くても一本一本作業を行います。
2回目は加工作業が終わった部材をもう一度削り、3回目の研磨へ移ります。
3回目はそれぞれのパーツを組み立ててから再度ペーパー掛けです。
4回目にさらにその部品を細かいペーパーで研磨し、5回目に極細ペーパーで仕上げを行い、全ての部品が組み立て終わった製品の完成形の状態で6回目の研磨作業が行われます。
ここまで繰り返し研磨作業を行うのは、「部材」の段階である程度仕上げても「部品」の段階までいくと他の部材との段差ができたり、細かなキズがついてしまうので、それを完全に無くしていくためです。
地道な作業ですが、ここで手を抜くと製品の完成度に響いてしまうので、丁寧な作業を心がけています。
| 塗 装 |
「新奥の表現を知る目。」
塗装は工程が多い作業の一つで、ここだけで約9つの工程を踏みます。
様々な塗装方法がありますが、今回は代表的なポリウレタン塗装についての工程をご紹介します。
まず第1の工程として、塗料が材料の中に浸透しやすい様にするため、表面を磨く研磨作業を行います。
次に第2の工程として、着色を行います。これは色付けの事を指します。
そして次に第3工程のサンディング、ポリウレタンを塗る下塗りをし、ここでは先ほど着色した色を抑える作業も行います。
第4工程では下塗りした塗料をさらに中へ浸透させるために、再び表面を磨く研磨を行います。
その後、第5工程として再度色を抑えるためのフラットポリウレタンを塗る捨塗り(すてぬり)を行います。
第6工程では表面の凹凸をなくすために最後の仕上げとしての研磨作業を行い、第7工程でカラーイングという色付け作業を行います。
そして第8工程であるフラットポリウレタンを塗り、最後の第9工程で乾燥室にて丸一日乾燥させ、全工程が終了します。
弊社製品は極力、無垢材の素材感を残すため、最後のポリウレタンは出来るだけ薄く塗布しています。
そのため、手で触ると木目を感じていただける仕上げとなり、お客様によってはオイル塗装と勘違いされる方がいらっしゃるくらい、しっとりとした風合いに仕上がっております。
| 調 整 |
「精緻を宿す指先。」
塗装終了後は、いよいよ最終調整です。
ここで金具類や引手の取り付け、ガラスのはめ込みなどの作業と、引出の収まり具合や扉の吊り具合などの調整作業を行います。
特に引出は組み立ての時点でも大まかな調整を行っていますが、最後に1杯1杯ペーパーで部品を削りながら、熟練の職人が収まり具合を見ながら調整を行います。
同じ大きさの引出でも1段目と2段目を入れ替えてみると、上手く入らないことがありますが、それこそが弊社製品が1つ1つ手作りであることの「証し」なのです。
そして細かい傷の有無等を点検後、梱包されて出荷となります。
ここに至るまでの様々な工程の中でも細かく製品チェックを行っていますが、見逃してしまったり、無垢材を使用しているが故に天板等は若干の反りが出ている場合もあります。
そのため、調整工程の担当者は弊社の全ての製品に精通しており、細かな微調整ができ、どんなに細かな傷でも見逃さない的確な目と判断力が必要となります。
こうして約7つの工程を踏んで製品が完成します。もちろん完成までには機会を使用する場面もありますが、どの工程においても手作業が大部分を占めています。
完成までには、およそ1ヵ月半ほどの期間を要しますが、木材の乾燥まで含めると1年以上の時間がかかっていると言っても過言ではないのかもしれません。